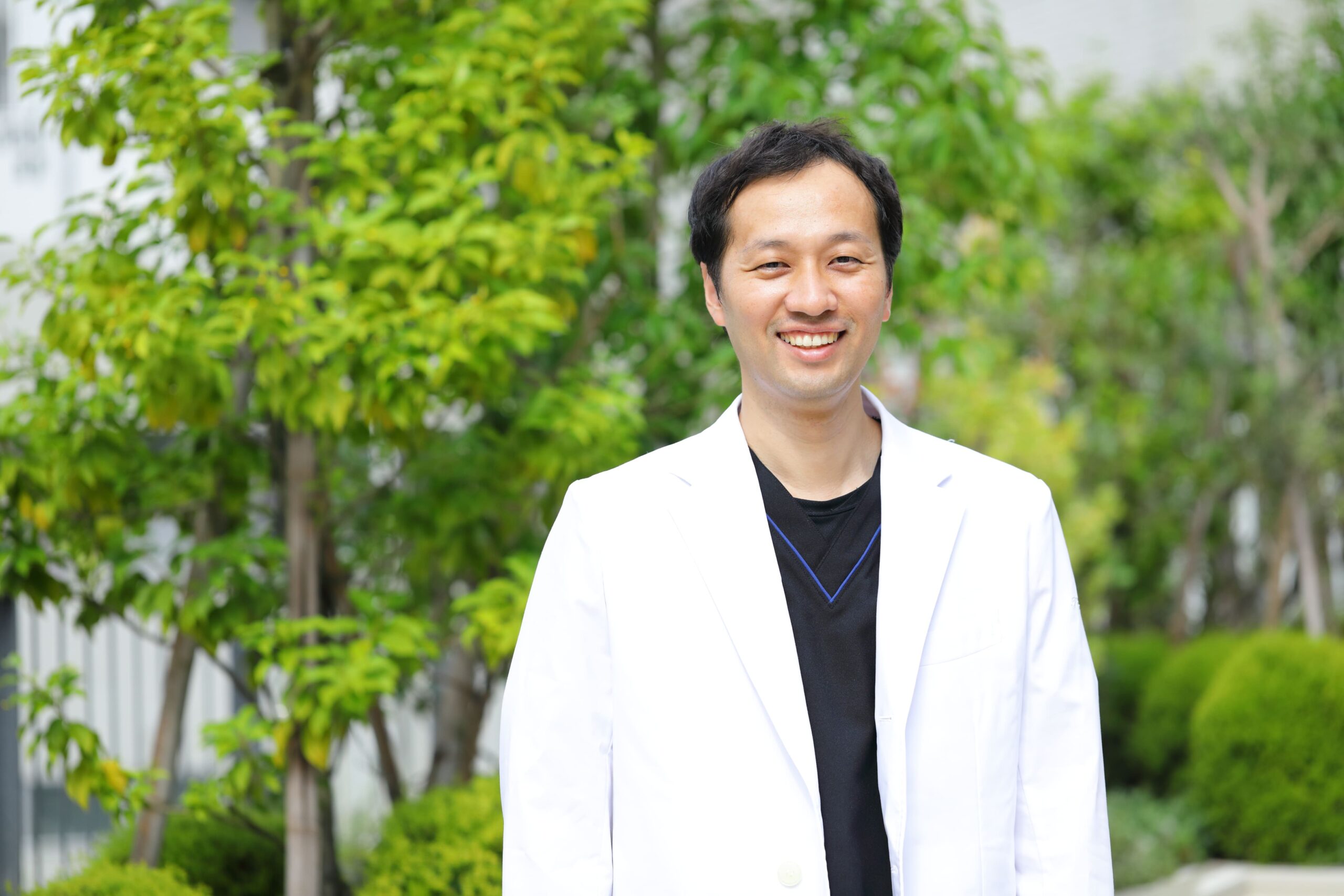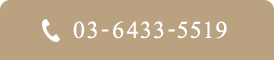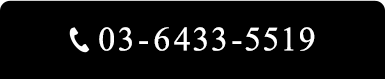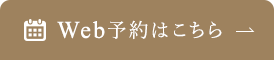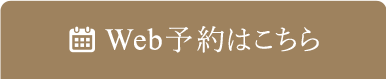女性特有の病気について不安を抱えている方に向けて、ASC-USの再検査について解説する記事です。
細胞診検査で「ASC-US」と判断されて要再検査とされれば、「子宮頸がんでは?」と不安になることでしょう。
再検査の日まで不安感が募ったり、子宮頸がんならどのような治療をするのだろうと思ったりするはずです。
そこで今回の記事では、ASC-USと判断された場合の再検査の方法3種と、子宮頸がんの進行段階について解説します。
参考にしていただければ、ASC-USだとされたときの不安感が和らぐはずです。
「ASC-US」についてよく分からない方は、まず以下の記事からご覧ください。
関連記事:ASC-USとは?ASC-USの原因や子宮頸がんとの関連について
■関連ページ
子宮頸がん検査の結果の分類
子宮頸がん検査の結果は、次のように分類されます。
|
|
ベセスダ分類 |
クラス分類 |
概要 |
|
扁平上皮系 |
NILM |
Class I Class II |
異常なし、炎症あり、要定期検診 |
|
Class II Class IIIa |
軽い病変の疑いあり、要HPV検査もしくは細胞診再検 |
||
|
Class IIIa Class IIIb |
病変の疑いあり、要コルポもしくは生検 |
||
|
Class IIIa |
軽度異形成、HPV感染、要コルポもしくは生検 |
||
|
Class IIIa Class IIIb Class IV |
中等度異形成、高度異形成、上皮内がん、要コルポもしくは生検 |
||
|
SCC |
Class V |
扁平上皮がん、要コルポもしくは生検 |
|
|
腺細胞系 |
AGC |
Class III |
腺異型もしくは腺がんの疑い、要コルポ、生検、頸管、内膜細胞診、組織診 |
|
AIS |
Class IV |
上皮内腺がん、要コルポ、生検、頸管、内膜細胞診、組織診 |
|
|
Adenocarcinoma |
Class V |
腺がん、要コルポ、生検、頸管、内膜細胞診、組織診 |
|
|
other malig |
Class V |
その他の悪性腫瘍、要病変検索検査 |
子宮頸がんの原因
子宮頸がんにはさまざまな分類があると解説しました。
それでは女性はなぜ、子宮頸がんになるのでしょうか?3つの原因についてご紹介します。
原因1:HPVの持続的な感染
まずはHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が持続的に続くことです。
HPVは性交渉を行ったことのある女性であれば、ほとんどの場合で感染すると言われています。
しかし感染しても2年ほどで消滅するため、病気に至ることはあまりありません。
ただし場合によっては、HPVの感染が2年以上継続することもあり得ます。
長期にわたり感染が続くと子宮頸がんに進展することも考えられます。
したがってHPVの持続的な感染がきっかけとなり、子宮頸がんが引き起こされがちです。
関連ページ:HPVについて
原因2:体質
HPVは体質によって排除されにくく、子宮頸がんに進展することもあります。
人によってはHPVを排除しにくいHLA遺伝子を持っている場合も。
HLAの型によってはウイルスを排除しにくく、2年以上のHPV感染を許してしまうことがあります。
そのために子宮頸がんに至りやすくなってしまう体質の方がいることも事実です。
原因3:環境因子
環境因子によって子宮頸がんになりやすくなる方もいます。たとえばクラミジアやバクテリアが子宮頸部にいる状態です[1]。
子宮頸部の環境が変わって、がんになる確率が高くなるのではないかとされています[1]。
ASC-USだと判断されたときに、HPV感染だけでなくクラミジアやバクテリアが存在していることもあるでしょう。
環境因子がそろった状態であれば、子宮頸がんの可能性は高くなるかもしれません。
精密検査の項目
ASC-USと判断されて再検査を受けるとなった場合、どのような検査を受けるのでしょうか?
これから行われる検査がわからず、不安を感じられる方もいるかもしれません。
精密検査が必要とされた場合、主に行われるのは次の3つの検査です。
精密検査1:コルポスコピー検査
ASC-USの再検査として頻繁に行われるのが、「コルポスコピー検査」です。
コルポスコピー検査は膣から拡大鏡を挿入して、子宮頸がんの疑いがある周辺を観察する検査のことを指します。
検査のために切開が行われることもなく、組織が採取されることもありません。そのため低侵襲であり、痛みを感じずに受けられることがメリットです。
またASC-USとの判断が正しかったかどうか、詳細に検査できるのもメリットのひとつと言えます。
もし子宮頸がんの可能性があるとされれば、検査中に組織が採取されることもあります。
しかし大きな痛みはなく、手軽に受けられる検査だと言えるでしょう。
精密検査2:トリアージ精検
トリアージ精検は検診においてHPV検査が陽性であったすぐ後に実施される検査です[2]。
HPV検査において採取された組織を用いて実施するため、身体への負担はありません[2]。
精密検査3:ハイリスクHPV検査
ASC-USにおける再検査で最も推奨される検査です。
HPVのタイプを判定して、子宮頸がんになるリスクを判断するための検査です。
HPVの中には子宮頸がんを発症させやすいタイプもいるため、ハイリスクHPV検査を行うことにより発症の危険性を判断できます。
子宮頸がんの段階
それでは最後に、子宮頸がんの段階について見ていきましょう。
4つの段階があるので、もしもASC-USから子宮頸がんに進展した場合に備えて進展を知っておいてください。
段階1:異常なし
まずは「異常なし」と診断される段階です。その名の通りで異常がなく、がん細胞が見つからなかった場合の診断結果となります。
しかし異常なしであったとしても、カンジダ感染やHPV感染による炎症が認められることもあるでしょう。
もし炎症がある場合は、炎症に対する治療が行われることがあります。
段階2:CIN1・2
CIN1・2は軽度から中等度の異形成が見られる段階です。異形成とは細胞の形が通常とは異なっている状態のこと。
がんへと進展する可能性もなくはありませんが、その他の炎症などによって異形成が起こることもあります。
CIN1は軽度異形成であり、CIN2は中等度異形成です。
もし治療が必要となったとしても、大掛かりな手術は不要であることも多いでしょう。
段階3:CIN3
CIN3は異形成ではなく、上皮がんが認められた段階です。
子宮頸がんの一歩手前の状態であり、病院での治療が必要とされます。
細胞の異形成が起きている場所が多く、浸潤性がんと診断されることも少なくありません。
段階4:子宮頸がん
最終段階は子宮頸がんの診断です。
すでにがん細胞が認められている状態で、すぐに病院で治療を始めたほうが良いでしょう。
ただし子宮頸がんはその他のがんと同じように、4つのステージに分かれています。
したがって発見されたときのステージによって、がんの広さや治療方法が変わってくるでしょう。
【子宮頸がんに関連するページ】
ASC-USは再検査の結果を受けて対処を
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで、ASC-USの再検査についてご理解いただけたと思います。
ASC-USの再検査には3種類があり、精密検査の結果を受けて、子宮頸がんのリスクがあるかどうかが判定されます。
Ladies clinic LOG 原宿でもコルポスコピー検査や子宮頸がん検査を行っておりますので、検査を受けたい方はお気軽にご相談ください。女性の健康を守るために最大限のサポートをいたしますので、ご来院をお待ちいたしております。
▼LOG原宿での検査予約はこちらから
[1]参照:LSIメディエンス:(PDF)講演1 子宮頸がん

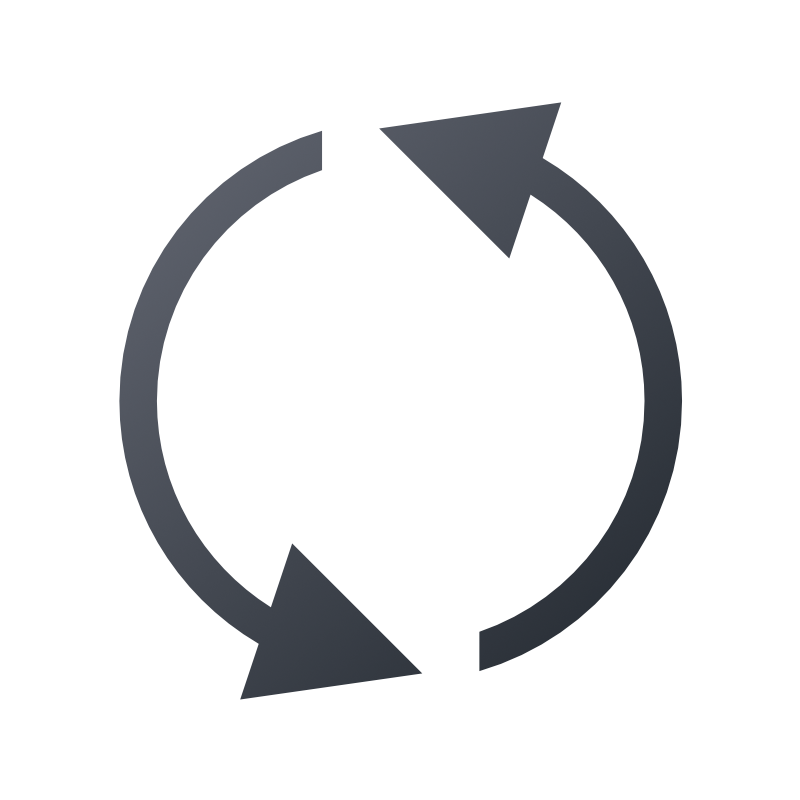 2025.03.28
2025.03.28