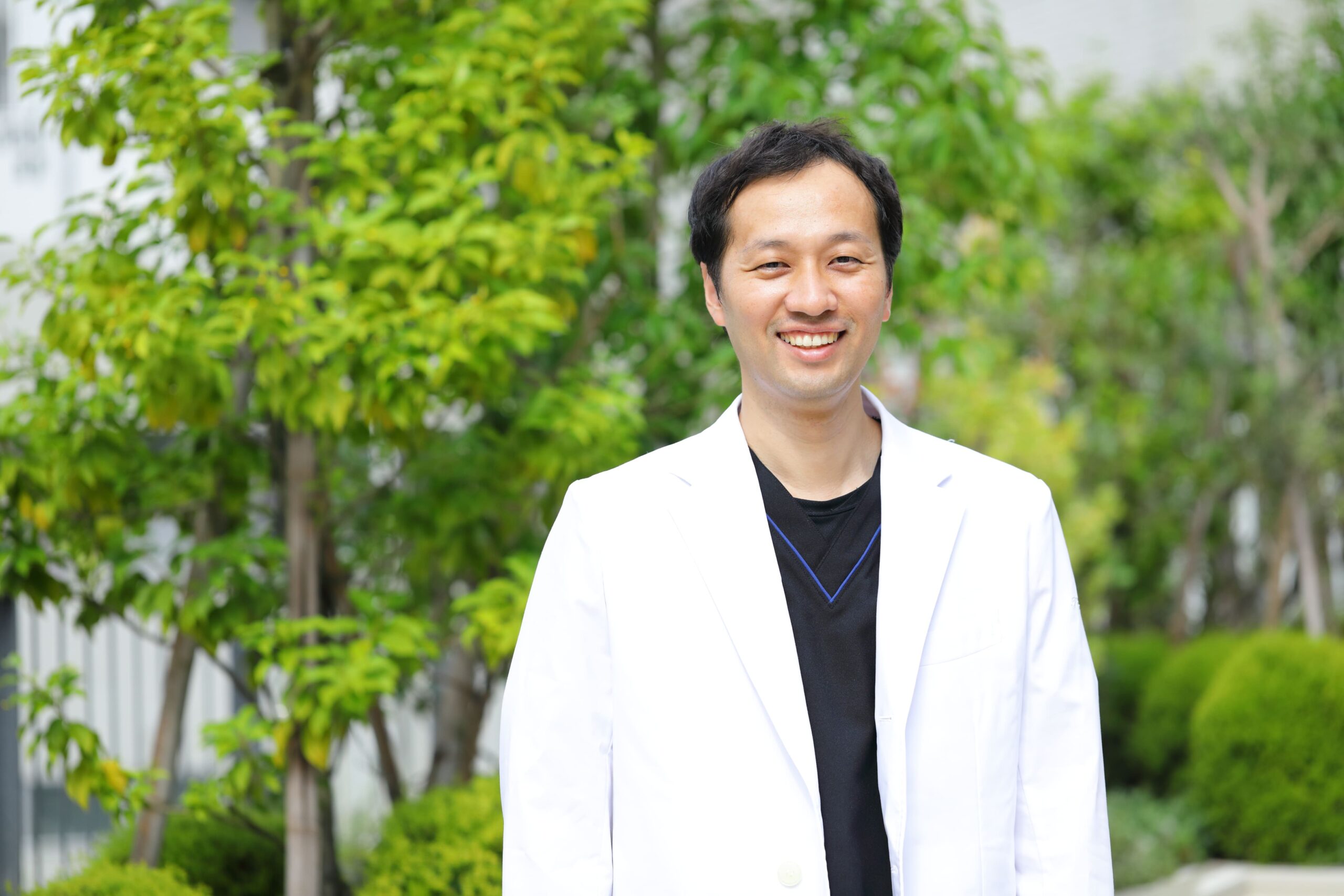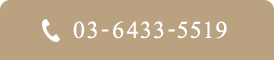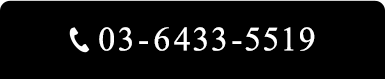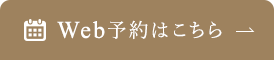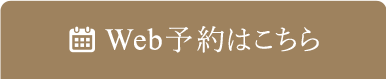子宮頸がんは、子宮の入り口(子宮頸部)に発生するがんのことです。
頸部は性行為や出産によって影響を受けやすい部位で、HPVウイルスと呼ばれるウイルスの感染にも注意しなければなりません。
HPVに感染すると、頸部の細胞が変化した「異形成」になります。検査では異常なしの状態から子宮頸がんまで、いくつかの段階に分けて頸部細胞の状態を検査します。
この記事では、ASC-USの分類とその内容、子宮頸がんとその他の分類の内容や治療方法について紹介します。
■関連ページ
ASC-USとは?
ASC-US(アスカス)は、病変があるかどうか判断がつかない状態です。
細胞診の段階で、通常とは細胞の形が変化しているものの、HPVウイルスとの関係があるのか、がんになる前段階・前がん病変(異形成)と関連しているかの判断がつかない場合にASC-USと診断されます。
子宮頸がんは、子宮頸がん細胞の約8割を占める扁平上皮系と呼ばれる部分と、残りの2割の部分(上皮内腺やその他の部位)に発生する病気です。
徐々に進行するのが特徴で、扁平上皮系の病変は陰性(正常)から癌化まで、次のように分類されています。
|
検査結果 |
分類 |
推定される病理(診断) |
|
陰性(異常なし) |
NILM |
非腫瘍性所見<br> 炎症 |
|
意義不明な異型扁平上皮細胞 |
ASC-US |
軽度扁平上皮内病変疑い |
|
軽度扁平上皮内病変 |
LISL |
HPV感染<br> CIN1 |
|
HSILを除外できない異型扁平上皮細胞 |
高度病変疑い |
|
|
高度扁平上皮内病変 |
CIN2<br> CIN3(高度異形成)・CIN3(上皮内癌) |
|
|
扁平上皮癌 |
SCC |
扁平上皮癌 |
ASC-USでは子宮頸がんを引き起こすとされるHPV(Human papillomavirus:ヒトパピローマウイルス)が関わっている可能性があります。
HPVウイルスは子宮頸がんを発症する方の99%が感染するため、HPV検査で感染状況を調べなければなりません。
HPV検査の結果が陽性(感染している)で、さらに症状が進行するとLISL(軽度扁平上皮内病変)となります。
生検やコルポスコピー検査と呼ばれる精密検査を行い、病変部をさらに詳細に検査します。
HPVに感染していない(陰性)場合は、年単位で検診を受けて経過を観察します。
ASC-USと診断されても、HPVが原因かどうかは検査によって判明するため、「感染症」「がん」といった状態にはありません。
検査と診断によって状態を確定させ、経過観察や治療を続けることが重要です。
関連記事:ASC-USとは?ASC-USの原因や子宮頸がんとの関連について
ASC-USと子宮頸がんの違い
ASC-USは「軽度扁平上皮内病変疑い」と推定され、明確な病変はありません。
細胞の形は陰性(正常)ではありませんが、異形成と呼べるほどの変化は少なく、明確に判断がつかない状態です。
この状態が進行すると「病変疑い」となり、異形成がみられます。
さらに異形成が進行すると、子宮頸がんと診断されます。
異形成はCIN(子宮頸部上皮内腫瘍)という表記で、3段階に分けて表されます。
CIN1は「軽度異形成」と呼ばれる状態で、消滅せずに感染が持続すると、HPVウイルスのDNAが子宮頚部細胞に組み込まれ、中等度・高度の異形成へと進みます。
子宮頸がんは、HPVウイルスに感染してから徐々に進行します。
すぐにがんが発生するわけではないため、初期のうちに検査し、診断にしたがって経過観察や治療を続けることが大切です。
関連ページ:子宮頸部異形成について
ASC-USでも精密検査が必要な理由
ASC-USは、何らかの原因で通常の細胞が形を変えている段階です。
通常の状態からわずかでも変化がみられるため、精密検査によって細胞の変化とHPVの関連を調べる必要があります。
HPVが影響している(陽性)場合は、将来的に異形成・がん化へと進むおそれがあるため、要経過観察となります。
異形成になっても、多くは自己免疫によって自然に消滅するといわれています。
しかし、異形成の一部はCIN2、3の病変に進行する可能性があるため、ASC-USの時点でHPVとの関係を明らかにしておく必要があるのです。
関連ページ:ASC-USでのがんの確率と子宮頸がんの段階や治療法について
精密検査でわかる子宮頸がんの段階
子宮頸がんは、精密検査によってどの状態にあるかを調べることができます。
子宮頸部の状態を検査し、「がんではないが進行する確率が高い状態」「悪性・良性の境界にある状態」などを段階的に診察します。
細胞がどの程度病変を起こしているのか、がん化するまでの経過を「異常なし」から「子宮頸がん」まで示します。
病変部の程度は、CIN(子宮頸部上皮内腫瘍)に数字を割り振ったもので示されます。
【経過割り振り】
- 異常なし
- CIN1・2
- CIN3
- 子宮頸がん
それぞれどのような状態なのか、詳しくみていきましょう。
異常なし
子宮頸がん細胞に変化がなく、陰性(異常なし)とされる正常な状態です。
子宮頸がんにおける扁平上皮系のクラス分類(ベセスダ分類)では、NILM(Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy)と表記され、異常なし・炎症ありと診断されます。
この段階ではまだ精密検査の必要はなく、定期検診のみで対応できます。
CIN1・2
CIN1は「(子宮頸部)軽度異形成」と呼ばれ、上皮の下1/3以内に異形成がみられ、留まっている状態です。
ベセスダ分類では「ASC-US」と表記されることもあります。
HPVウイルスによる病変なのか、それ以外の理由なのかを明らかにする必要があるため、精密検査としてHPV検査または細胞診による再検査となります。
CIN2は「(子宮頸部)中等度異形成」と呼ばれ、上皮の下2/3以内に異形成がみられ、留まっている状態です。
高度に扁平上皮内の病変疑いがあるCIN2とCIN3をあわせて「ASC-H」と表記されることもあります。
CIN1よりも異形成の範囲が広がり、CIN3からそれ以上に進行するリスクもあることから、精密検査としてコルポスコープ+生検(組織診)の再検査となります。
がん化しているわけではなく、自然に治癒する場合もある段階です。(※)
軽度異形成(CIN1)や中等度異形成(CIN2)はがんと呼べる状態ではありません。
免疫による自然治癒が期待できるため、精密検査のうえ経過観察を行うケースが多くみられます。
※メディカルオンライン「子宮頸部中等度異形成(CIN2)の進行リスクをメタ解析:2年で半数は退縮」
CIN3
CIN3は、「(子宮頸部)高度異形成」または「上皮内がん」と呼ばれる状態です。
高度異形成は上皮の下2/3以上に異形成がみられ、留まっている状態です。
上皮内がんは、すでに上皮の全層が異形のある細胞に変化し、留まっている状態です。
この段階でもまだ軽度異形成へと退縮する可能性がありますが、約10%は浸潤がんへと進行する可能性があります。
CIN2〜CIN3が長期間持続する場合は、自然治癒が難しいとして治療を選択することもあります。
※参照元:慶應義塾大学病院 KOMPAS「子宮頸部異形成に対する子宮頸部レーザー蒸散術」
子宮頸がん
子宮頸がんは、CIN3の高度異形成・上皮内がんがさらに進行し、浸潤がん化した状態です。
がん化の程度に応じたステージ分類は次のとおりです。
|
期間 |
状態 |
|
0期 |
粘膜内にとどまっているがん(上皮内がん) |
|
Ⅰ期 |
子宮頚部に限るが、粘膜から浸潤を始めた状態 |
|
Ⅱ期 |
子宮頸部を超えて骨盤内にがんが広がっている状態 |
|
Ⅲ期 |
骨盤壁または膣の下方3分の1までがんが達した状態 |
|
Ⅳ期 |
膀胱や直腸・他の臓器までがんが遠隔転移した状態 |
患部が限局している場合は摘出手術や切除手術が選択されますが、Ⅲ期以降は放射線療法や化学療法などが行われます。
関連ページ:子宮頸がんについて
子宮頸がんの治療方法と術後の影響
子宮頸がんの治療方法は、次の3種類に分けられます。
【子宮頸がん3種類】
- 手術
- 放射線治療
- 薬物療法
それぞれの治療方法と術後の影響についてみていきましょう。
手術
手術は、すでに浸潤がんとして子宮頸部やその他の部位に及んでいる場合に、患部を取り除く目的で行われます。
「子宮頸部円錐切除術」と呼ばれる方法は、子宮頸部(子宮の入り口にあたる部分)を円錐形に切除する方法です。
子宮頸部円錐切除術は腫瘍が子宮頸部に限られている症例に適した方法ですが、診断を目的として行われる場合もあります。
CIN3などと診断されても、浸潤がんが併存している可能性があるため、確定診断のために手術が行われます。
円錐切除術は子宮の大部分を残せるため、妊娠や子宮の温存を希望する患者さんにも適しています(温存が不要な場合は、子宮全摘出術が選択できます)。
※参照元:東邦大学医療センター 大橋病院産婦人科「子宮頸部異形成について」
放射線治療
放射線治療は、細胞内のDNAを破壊する力があり、X線やガンマ線をがんに直接当てて治療する方法です。
骨盤の外から照射する「外部照射」と、子宮などに器具を入れて子宮頸部に照射する「腔内照射」、放射線を出す物質を患部とその周辺の組織内に挿入する「組織内照射」があります。
放射線治療は、あらゆる病変や経過に対応できる方法です。
がんに直接作用させる目的以外では、手術後の再発予防や細胞障害性抗がん薬との併用(進行したがんに対して行う)も行われます。
高齢の方や合併症がある方にも適用でき、侵襲のリスクがある手術よりも排尿機能などへの影響が少ないとされていますが、既往症や体調への影響も考慮する必要があります。
主治医とよく話し合って放射線治療を検討することが大切です。
薬物療法
薬物療法は、浸潤がんが進行し遠隔転移がある場合や、再発がんに対して行われる方法です。
ステージが進行した方にも、生活の質(QQL)を保ちながら生存期間を延ばすために実施されています。
代表的な薬物に「細胞障害性抗がん薬」と「分子標的薬」があります。
細胞障害性抗がん薬は、細胞の増殖を阻害してがん細胞を攻撃します。分子標的薬は、がん細胞を増殖させるタンパク質をターゲットとして攻撃する薬です。
ASC-USは放置せず検査を受けることが大切
今回は、子宮頸がんの特徴や進行度・治療の方法について紹介しました。
子宮頸がんは若年層でも罹患する病気で、性行為によって感染する病気の一つです。
ストレスや生活習慣の影響を受けて起こる不正出血とも混同されやすく、初期の段階で気づきにくいといった問題もあります。
免疫によって治る確率が高いのは、ASC-USを含めた初期〜中期の段階です。それ以降は持続感染やがんとの併存、浸潤がんへと進むおそれもあります。
がん化した部位は手術や放射線治療を実施しなければならないため、早期発見・早期治療を心掛けることが大切です。

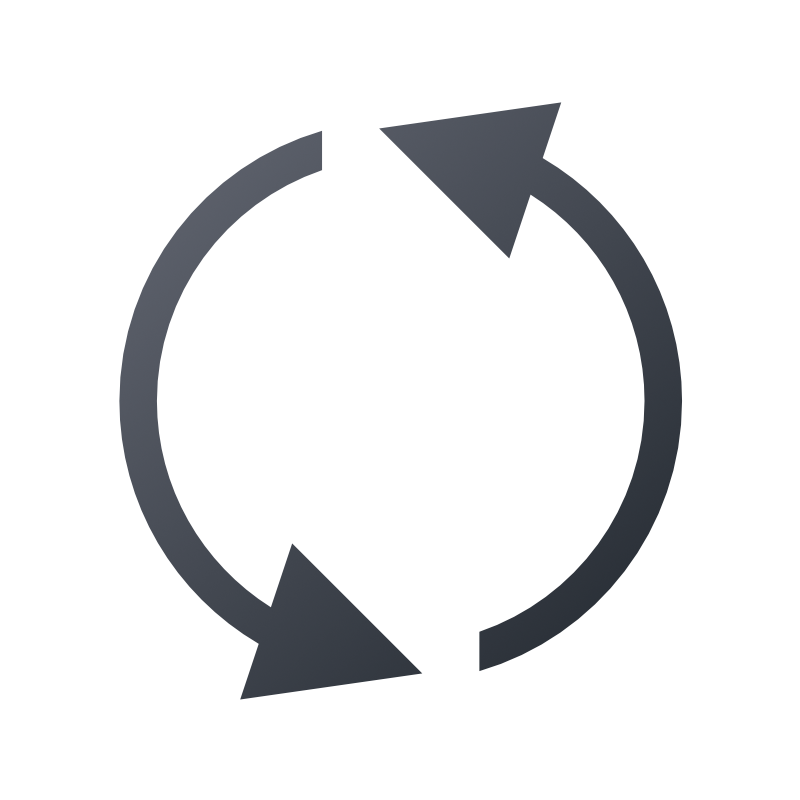 2025.03.27
2025.03.27