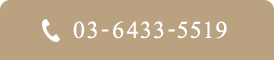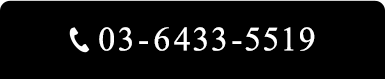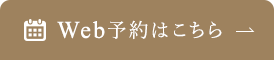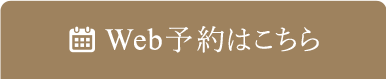女性特有の病気への不安がある方に向けて、ASC-USでの子宮頸がんの確率について解説します。
もし検診で「ASC-US」と判断されたら、「がんなのでは…」とご不安でしょう。
要精密検査と言われたものの、今後どのような検査が行われるのだろうと心配になる方もいらっしゃいます。
そこで今回の記事では、ASC-USでの子宮頸がんに進展する確率や、子宮頸がんの検査方法・治療法について解説します。
参考にしていただければ、これからどのような検査や治療が行われる可能性があるかがおわかりいただけるはずです。
■関連ページ
ASC-USとは?
「ASC-US」とは異形成の疑いがある状態のことです。
異形成とは細胞の形が通常とは異なっていることで、がんではありません。
しかしASC-USと判断された方の中には、低い確率で子宮頸がんが発見されることもあります。
多くの場合は炎症による細胞の変形であったり、がんの前段階であったりでASC-USと判断されるでしょう。
そのため過度な心配は入りませんが、異形成はがんとなる可能性があることも知っておいてください。
関連ページ:子宮頸部異形成について
細胞診でわかること
細胞診は子宮頸がんの検査のために行われます。
細胞診にはいくつかの分類があり、検査結果に応じていずれかのグループに分類されます。
それでは細胞診ではどのようなことがわかるのでしょうか?下記の3つのことを確認するために細胞診が行われます。
わかること1:子宮頸がんの可能性があるか
わかることのひとつめは、子宮頸がんの可能性についてです。
もし可能性が高いと判断された場合は要精密検査となり、可能性が低ければ精密検査不要との結果が出ます。
特に異常が見受けられなかったときは「NILM」との分類になるので、引き続き、2年に一度の子宮頸がん検診を続けましょう。
細胞診では以上のように、子宮頸がんへと進展する確率とともに、精密検査の必要性があるかどうかを診断できます。
わかること2:異形成の可能性があるか
異形成の可能性も細胞診検査にてわかることのひとつです。
異形成とは細胞が通常とは違った形状になっている状態のことを指します。
がんではない可能性が高く、HPV(ヒトパピローマウイルス)やカンジダ感染による炎症で細胞が異なる形状になっていることがほとんどです。
しかし通常とは異なる形状の細胞から子宮頸がんへと進展することもあり得ます。
また炎症が起きているのであれば、炎症を収めるための治療が必要となるでしょう。
細胞診は子宮頸がんの可能性だけでなく、子宮周辺の細胞の正常性も判断できる検査です。
わかること3:そのほかの異常があるか
最後に、そのほかの異常についてです。
細胞診では子宮頸部の組織を採取して検査するため、そのほかの異常について診断することもできます。
たとえば子宮体部や卵巣に異常がないか、子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣嚢腫の可能性がないかなどです。
最近では細胞診とともに、超音波検査を行うことも多くなってきました。
せっかく細胞診検査を受けるのであれば、子宮や卵巣にそのほかの異常がないか、検査されることをおすすめします。
▼LOG原宿での検査予約はこちらから
ASC-USを引き起こす原因
ASC-USが引き起こされる原因は、主にHPVへの感染です。
HPVは性交渉や皮膚の接触により感染するウイルスで、性交渉を行ったことのある女性のほとんどが感染します。
通常は免疫細胞により排除され、約2年の感染期間を経て無効となります。
しかしまれに2年以上も感染が持続することがあり、長期にわたる感染によって細胞が異形成される可能性も。
しかしASC-USの段階では、ウイルスによって細胞の形状が変化した程度で収まっていることがほとんどです。
経過観察しているうちに、自然に消滅していることもあります。
しかしASC-USの原因になることは確かだと考えられています。
子宮頸がんの患者の年齢層
子宮頸がんの患者様の年齢層は、最近では20~40代が中心となっています[1]。
1985年には50代以上の女性でリスクが高まっていました[1]。しかし2019年には20代後半から発症の比率が増えています[1]。
2000年には若い方の感染率は低下しましたが、やはり30代からの発症は少なくありません[1]。
そのため若いからと言って油断はできません。20代後半からは、定期的に子宮頸がんの検診を受けられることをおすすめします。
子宮頸がんの段階
ASC-USからがんへと進行する確率は高くありません。しかしやはり、子宮頸がんへと進展することもあり得ます。
そこでもしもASC-USと判断された場合に備えて、子宮頸がんに進展する段階について知っておきましょう。
4つの段階があり、どの状態であるかによって対処や治療も変わります。
段階1:異常なし
子宮頸がんの兆候がなく、細胞にも特に異常がないと判断される段階です。
もしASC-USと判断されていたとしても、HPVやカンジダ感染による炎症によって通常とは異なる形状の細胞が見られたと考えられるでしょう。
もちろん子宮頸がんの治療を受ける必要はありません。
しかし炎症が起きているとしたら、炎症を抑えるための治療は必要となることがあります。
段階2:CIN1・2
細胞の形状の変異において、CIN1は軽度、CIN2は中等度で変異している段階です。
通常とは異なる形状の細胞は確かにあるものの軽く、子宮頸がんになる可能性もある状態のことを指します。
軽度であるCIN1よりも、CIN2の方が進展の可能性は高くなります。
ただしまだ子宮頸がんとは言えず、経過観察となることもあるでしょう。
段階3:CIN3
CIN3は通常とは異なる形状の細胞が上皮から1/3以上に及んでおり、子宮頸がんになるリスクが高いとされています。
浸潤性がんであるとの診断が下ることもあるでしょう。
ただしまだ子宮頸がんとは言えないレベルであるため、できる限り早めの治療開始が求められます。
段階4:子宮頸がん
がん細胞が認められ、子宮頸がんであると診断される段階です。
すでに子宮頸がんであり、病院での治療は必須と言えるでしょう。
しかしそのほかのがんと同じように、子宮頸がんにも4つのステージがあります。
ステージによってがんの進行具合が変わるため、採用される治療法も変わります。
ステージ内でもさらに細かく分類されるため、より精密な検査により状態を把握し、治療を進める流れです。
関連ページ:ASC-USでがんだったらどうする?がんの段階と精密検査について
子宮頸がんの症状
それでは続いて、子宮頸がんの症状について見ていきましょう。
【症状】
- 不正出血
- おりもの
- 性行為中の出血や痛み
- 月経過多
初期症状がないことが多いため、気づいたときには進行しているケースも多いのが子宮頸がんです。
特にもともと経血量やおりもの量が多い方は気づきにくい傾向があります。
上記のような症状が出たときはもちろん、やはり定期的に検診を受けると安心でしょう。
子宮頸がんの検査方法
子宮頸がんの検査は視診、内診、頸部細胞診、HPV検査の4種類にて行われます。
検診を受けようとしても、どのような検査が行われるかわからなければ不安な方もいらっしゃるはずです。
受診前に検査方法の概要についてご紹介します。
検査1:視診
視診は子宮頸部を直接観察する検査です。膣の中に腟鏡と呼ばれる器具を挿入して観察します。
確認できるのは目で見てわかるほどの腫瘍や炎症などです。
視診だけではわからない部分も多いため、ほかの検査と組み合わせて行われるでしょう。
検査2:内診
続いての内診は、膣内に指を入れて触診をする検査のことを指します。
子宮と卵巣の状態を確認するための検査です。大きさや形状に異常がないかがわかります。
検査3:頸部細胞診
頸部細胞診とは子宮頸部の組織を採取して行う検査です。
膣から器具を挿入してごくわずかな組織を切除して検査をします。
検査結果は「ベセスダシステム」と呼ばれる分類で提示され、「ASC-US」などの分類によってがんの確率がわかる仕組みです。
検査4:HPV検査
HPV検査はHPV(ヒトパピローマウイルス)への感染状況を調べるための検査です。
HPVは子宮頸がんの原因となります。性交渉を行ったことのある女性であれば、高い確率で感染するウイルスです。
しかし中には子宮頸がん罹患リスクを高めるタイプのものがいます。
頸部細胞診で採取した組織を用いて、子宮頸がんのリスクがどのくらいであるかを調べます。
子宮頸がんの治療法
それでは最後に、子宮頸がんの治療法についてご紹介します。
主に採用されるのは次の4つです。
治療法1:手術療法
子宮頸がんが発生している部分を切除するのが手術療法です。
子宮全体を切除することもありますが、一部のみの摘出で済むことも珍しくありません。
外科的手術なので不安が大きい方もいるかもしれません。
実際に身体への負担は大きい治療法です。しかし子宮全体の摘出であれば再発のリスクを軽減できるメリットがあります。
進行しているタイプの子宮頸がんに採用されるでしょう。
治療法2:抗がん化学療法
抗がん化学療法とは、抗がん剤による治療のことです。最後に解説する放射線治療と組み合わせられるケースが多く見られます。
血管新生阻害薬と併用されることも少なくありません。
進行したタイプの子宮頸がん治療に用いられることが多いのが抗がん化学療法です。
副作用がありますが、近年では副作用が抑えられたタイプの抗がん剤もあります。
治療法3:免疫チェックポイント阻害剤での治療
がん細胞を排除するために、免疫チェックポイント阻害剤が用いられることがあります。
免疫チェックポイント阻害剤ではがん細胞の活性化を抑え、免疫細胞の活性を促せます。
抗がん化学療法とともに用いられる治療法であり、進行もしくは再発した子宮頸がんに使われるのが一般的です。
治療法4:放射線治療
放射線を照射してがん細胞にダメージを与えるのが放射線治療。そのほかのがん治療においても、抗がん化学療法とともに広く知られている治療法です。
外から照射する外部照射と、膣から器具を挿入して直接がん細胞に照射する腔内照射の2種類があります。
進行した子宮頸がんの場合は抗がん化学療法と併用されることが多く、再発のリスクも軽減可能です。
卵巣は機能しなくなるものの、身体への影響が小さいことがメリットでしょう。
ASC-USは子宮頸がんの確率を示唆するもの
いかがでしたでしょうか?この記事を読んでいただくことで、ASC-USにおける子宮頸がんの確率についてご理解いただけたと思います。
ASC-USと判断されても、子宮頸がんになる確率は低いと言えます。しかしゼロではないため、検査や治療などの適切な対応が重要です。
Ladies clinic LOG 原宿では子宮頸がん検診やワクチンの接種に対応しています。「もしかしたら」と不安に思われているようでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
▼LOG原宿での検査予約はこちらから
[1]
参照:国立がん研究センター:(PDF)知ってくださいヒトパピローマウイルス(HPV)と子宮頸がんのこと
監修者
院長
清水拓哉
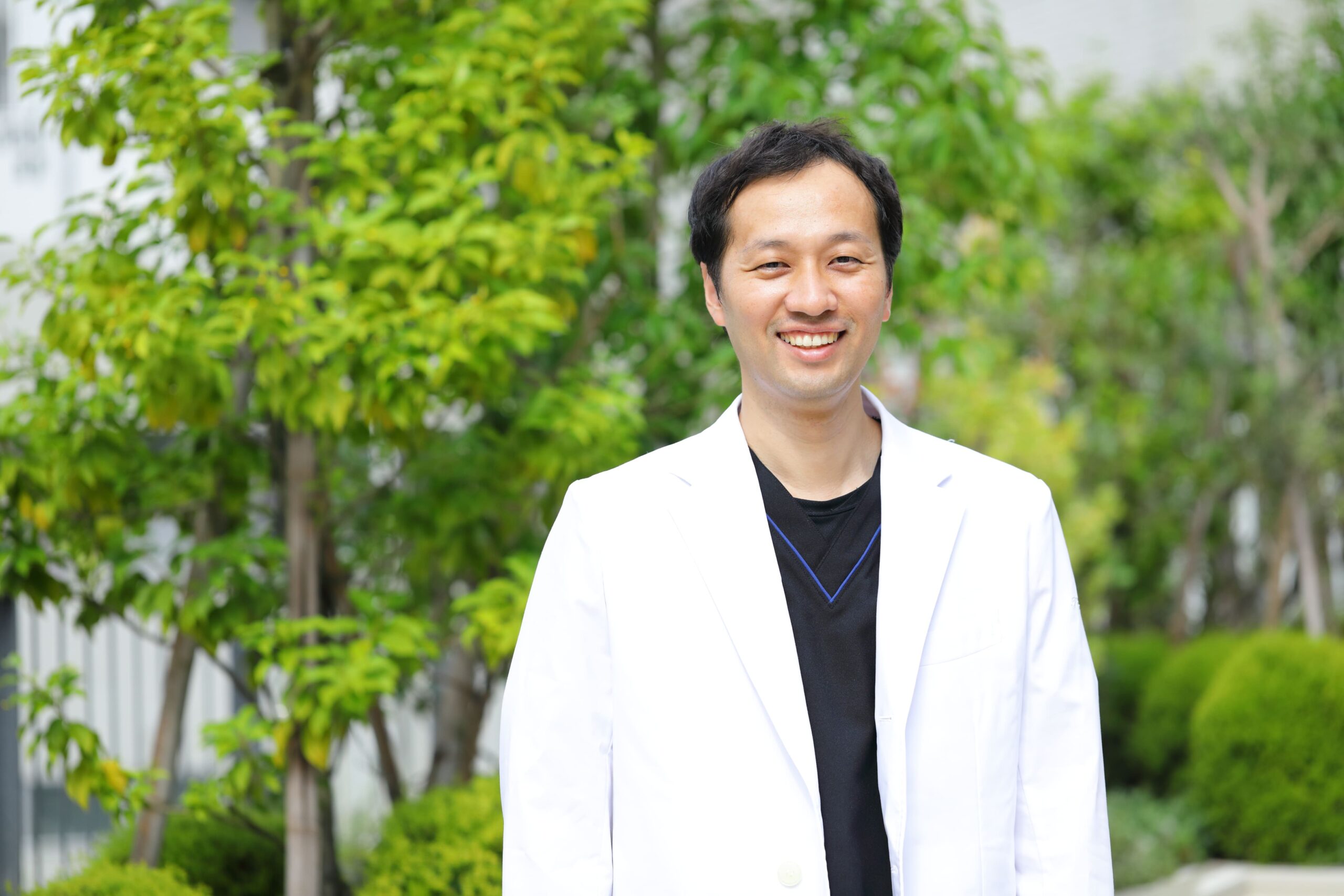
経歴
- 杏林大学医学部卒業
- 筑波大学附属病院初期研修
- けいゆう病院後期研修
- 横浜総合病院などで勤務した後に開業
資格
- 日本産婦人科学会専門医
- 産婦人科内視鏡技術認定医
所属学会
- 日本産婦人科学会
- 日本産婦人科内視鏡学会
- 日本子宮鏡研究会
手術実績(通算)
- 腹腔鏡手術・700件以上
- 開腹手術・150件以上
- 帝王切開・300件以上
- 分娩(経腟分娩)・1000件以上

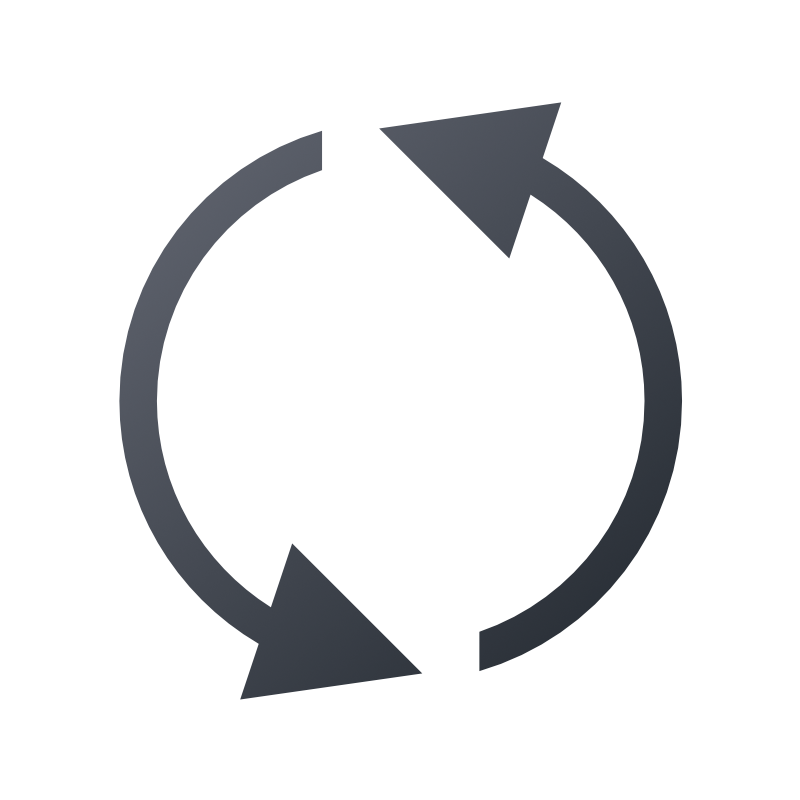 2025.03.28
2025.03.28